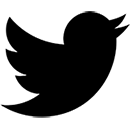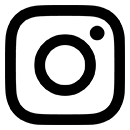トップページ >館長からのメッセージ >わが国の近代美術館事情35
わが国の近代美術館事情35
(4)「和歌山県立近代美術館」の昨日、明日―その32
当館では、7月から1階・2階ともに新たな展覧会がはじまっている。2階は、12回目を数える「なつやすみの美術館」。今回は、湯浅町出身の妻木良三氏をゲストに迎え「はじまりの風景」をテーマに、妻木氏の作品と妻木氏が選び、集めたものを共に展示している(9月4日まで)。
妻木氏は、有田郡湯浅町にアトリエを構えて作家活動を続けているが、同地で400年続くお寺の住職でもある。武蔵野美術大学で油絵を学び、1998年から鉛筆による絵画を描き、個展のほか、VOCA展や目黒区美術館の企画展、ミュンヘンでも作品を発表し、和歌山県文化表彰文化奨励賞も受賞されている。
そして1階の「コレクション展2022―夏秋」では、特集展示として「1960s–1980s 関西の現代美術『再見』」展を9月25日まで開催している。この1階と2階で開かれているふたつの展覧会を対比させて見ることができる。
「はじまりの風景」展では、妻木氏の出品作が、ほぼすべて2010年代の制作になるという、まさに「現代美術作品」である。しかもこれらの作品は、鉛筆で描かれ、あたかも絵画における表現行為の「はじまり」を示しているかのような気分に包まれている。
一方、1階の「コレクション展」には、それより40年以上も前の1980年代に生み出された作品をはじめ、1960年・70年代の、これも「現代美術」と呼ばれる作品を集めている。だが、これらの時代の「現代美術」を特集展示した「コレクション展」に、妻木氏のような鉛筆で描かれた作品は1点もない。一方、1980年代から40年以上も経って制作された妻木氏の作品は、いずれも古典的な「風景画」と見紛うものであり、同時にその「表現」についても考えさせられる。
1960年代以降、1階の「コレクション展」に見られるように、とりわけ新しい表現を求めて活発な活動が繰り広げられた一群の「現代美術」作品がある。そしてまさしく現代に、僧侶のように時代を超越したかのごとく、鉛筆だけをにぎって寡黙に制作を続ける妻木氏の作品もまた、「現代美術」にほかならない。
1980年代は、たとえば当時の兵庫県立近代美術館の1,300平米の大展示室で開かれた「アート・ナウ」展が象徴するように、出品作家たちは競うように奇抜な大型作品を発表していった。この活発な表現活動は、東京に対しても「西高東低」と評価され、関西の「ニューウェーブ」と呼ばれて注目を浴びた。
1階の「コレクション展」では、60年代から80年代に開催されていた「現代美術展」の状況を示す会場写真の資料や図録とともに、1986年2月28日付の朝日新聞(夕刊)を並べて紹介した。その記事には、「若者たちの巨大な実験」「時代を先取り、型破りな感性」という見出しがおどる。しかし、それから40年近くを経て、それらの作品は、文字どおり「時代を先取り」したものだったかと、2階に展示された妻木氏の作品を見てあらためて感じてしまう。
この兵庫県立近代美術館の「アート・ナウ」は、関西にはじめて誕生した近代美術館である現在の京都国立近代美術館で、1963年の開館時に開催された「現代絵画の動向」、そしてその後も「現代美術の動向」や「現代美術の鳥瞰」展として継続して開かれてきた展覧会を、まさに引き継ぐかたちで、1975年から開催された。
今回の「コレクション展」でも、1960年代から80年代の「現代美術」の展開を紹介するに際し、「現代美術の動向」や「アート・ナウ」に出品された作家とともに、当館で1983年から1991年まで8回開催した「関西の美術家シリーズ」で取り上げられた作家の作品も紹介している。
また当時、関西の近代美術館で企画された展覧会として注目すべき「今日の100人」展(兵庫県立近代美術館、1971年)に、すでに当館所蔵になる高井貞二の《赤と金》(1962年作、当時の出品作品名は《金と銀》)や、村井正誠の代表作《風の中の除幕式》(1968年)が、同じく和歌山ゆかりの宇佐美圭司、松谷武判、建畠覚造や保田春彦らとともに出品されていた。その翌1972年には、当館でも「現代日本絵画秀作展」を開催し、関西の近代美術館で数多くの「現代美術展」が開かれていった。
しかしながら、こうした展覧会の企画・開催だけでなく、作品収集という「コレクション」の視点から、当時の関西の「近代美術館」の状況を見つめ直せば、当館が他館に先んじて、いち早く作品収集にも着手してきたことがわかる。コレクションだけで、1960年代から80年代をふりかえることができるのも、関西の美術館では当館だけだろう。
私は、兵庫の近代美術館に勤務して7年目の1986年から88年ごろまで、その「アート・ナウ」展の作品集荷や展示、さらに図録作成を担当していたことがある。それまでに自ら企画した展覧会はいくつかあったものの、若い作家たちと接する機会は、はじめてだった。出品作家は、選考委員会の委員の方々が、各自推薦する作家の作品をスライドで提示しながら討議し、決定されていった。その委員会が開かれた会場の片隅で、出品作家が決まっていく状況を見ていた。そして出品作家たちと、作品集荷から展示にいたる「美術の現場」の最前線に立ち会っていたことは間違いないが、そうした貴重な体験を後に生かす余裕がなかったことは残念でならない。
そうした思いもあり、戦前の動向も含めながら、「コレクション展2022―夏秋」の特集「1960s–1980s 関西の現代美術『再見』」展を、今回企画した次第である。
加えて、和歌山に着任してから、あるコレクション展で、当時、集荷から展示までを担当した「アート・ナウ」に出品され、図録の表紙にも掲載した作品が、当館に収蔵されていることを知って驚いたのも契機となっている。
それが、今回出品した川島慶樹氏の《Yellow Vacation II》(当時の作品名は《UNTITLED》)である。しかもキャプションを見て唖然としたのは、その作品が「アート・ナウ」出品の翌年に、なんと作者寄贈で当館のコレクションになっていたことだ。当時の兵庫県立近代美術館は、「アート・ナウ」の出品作をコレクションしようという動きはなかった。
2階に展示された妻木氏の展覧会には、岸田劉生の《天地創造》や日和崎尊夫の版画と響き合うように、和歌山県立自然博物館や妻木氏所蔵の「化石」やさまざまな生物の骨なども並べられている。それらは、確かに妻木氏の作画イメージの源泉を示し、生命について、あるいは過去から現代までの壮大な「時間」についても問いかけているようだ。
そして1階の「コレクション展」では、「序章」に「戦前の日本の前衛」として、多くは人物をモチーフとしながらも、その「脱対象化」を狙った作品を集めた。これらの作品は、戦後の「現代美術」にも持続される、確かな源泉を形成しているだろう。今回のふたつの展覧会を機に、あらためて「現代=モダン」の意味についても再考いただけるのではないかと思う。