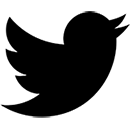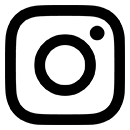トップページ >館長からのメッセージ >わが国の近代美術館事情36
わが国の近代美術館事情36
(4)「和歌山県立近代美術館」の昨日、明日―その33
この「館長メッセージ」も少し間があいたが、今年2月からは「とびたつとき 池田満寿夫とデモクラートの作家」展もはじまり、早いものでこの展覧会も4月9日(日)には最終日を迎える。その後は、宇都宮美術館、長野県立美術館、そしてリニューアルされた広島市現代美術館の各会場を、来年の3月まで巡回する。
「とびたつとき」展は、当館のコレクションの柱である版画作品も多数出品され、かつて当館で開催された「デモクラート」についての決定版ともいうべき展覧会である「デモクラート 1951–1957 解放された戦後美術」(1999年)を呼び起こす上でも意義深いものとなった。そして私も、展覧会図録で、デモクラート美術家協会結成の地となった大阪の美術界の動向を再考する機会を得たが、ここで思いもかけない「展覧会の連なり」を実感した。
それがこの「とびたつとき」展と、昨秋、当館の特別展として開催した「稗田一穗展」である。稗田は、1930年代の大阪市立工芸学校(現大阪府立工芸高等学校)で学び、後年、デモクラートに参加することになる早川良雄や泉茂たちもまた、同時代にこの学校で学んでいたのである。
そして私には、学芸員としてはじめて企画した「大阪・神戸のモダニズム 1920-1940」展(1985年)で、「大阪のモダニズム」の視点から、大阪市立工芸学校創立当初の1920年代の活動を紹介した懐かしい思いがある。その際、同校の職員室を訪ね、早川や山城隆一らの連絡先も教えていただき、当時のことを取材した。さらには同校の職員室に眠っていた本館校舎の竣工時の建築図面や、図書台帳などを先生とともに発見したのだった。
そうした繋がりもあって、創立70周年の記念事業として刊行された『大阪市立工芸高等学校70周年記念誌 時代・社会・デザイン』(1993年)で、バウハウスに統合された旧ヴァイマールの工芸学校を模したといわれる同校の本館校舎について紹介した。そして「稗田一穗展」で、同校をふたたび訪問し、『藝草』と名づけられた創立時の学校機関誌を閲覧させていただき、稗田や早川の名を見つけ、思いもかけない結びつきを実感したのである。この『藝草』は、1929年の12月に創刊され、1964年5月までに40号を数えた。しかし、戦時中には一時廃刊され、『報国団報』とその名も改められたというが、後年の創立60周年記念誌では、『芸草』の名が復活したように掲げられていた。
ところで「とびたつとき」展や、これも現在開催中の「コレクション展 2023–春」の特集「新収蔵 奈良原一高の写真」(5月7日まで)などについては、次回あらためて記したいと思うが、「稗田一穗展」とほぼ同時期(2022年の10月から12月まで)に開催していた「ミティラー美術館コレクション展」にも、さらなる意外な「展覧会の連なり」を感じる。
和歌山県とインドの交流という視点を再認識する上でも貴重な企画であるこの展覧会は、2013年に和歌山県とインド・マハラシュトラ州との間で覚書を締結し、10周年を迎える友好交流事業として開催された。昨年はまた、日印国交樹立70周年の記念すべき年でもあった。和歌山・インドの相互交流の実現に際しては、仁坂吉伸前和歌山県知事3度インドを訪ねられ、交渉を積み重ねてこられた経緯がある。また昨年末、新たに知事に就任された岸本周平知事も、この2月初めには、早速マハラシュトラ州ほかを訪問されている。
そして、和歌山県と当館が主催し、和歌山県とインド・マハラシュトラ州との友好交流によって、新潟県十日町市にある私設のミティラー美術館が所蔵するインドの多様な現代民族芸術を網羅したコレクション展が開催の運びとなったのである。西日本で、ミティラー美術館のコレクションを披露するのもはじめてのことであった。
特筆すべきは、このコレクションが、現代に息づく性格を有していることにある。長谷川時夫館長も指摘するように、「今回展示された作品のほとんどは、インドで生まれた絵画をコレクションしたものではなく、インドのフォークアートの描き手たちが何千キロも離れた日本にやってきて、ミティラー美術館の活動に参画しながら、当館や日本の全国各地で公開制作を行なったことで生まれたもの」(長谷川時夫「ミティラー美術館コレクション展によせて」、『和歌山県立近代美術館ニュース』No.114、2023年)なのである。展覧会の出品作も、1990年から2000年はじめに制作された作品群であり、ミティラー美術館は現代美術館と言って過言ではない。
しかもこうした作品から響く現代感覚は、長谷川館長の希有な活動によって磨かれてきた。それは長谷川館長が、1969年に結成されたタージマハル旅行団の結成に参加した、現代音楽奏者であることとも連なっている。ジャズ、ロックといったジャンルを超えて、電子音楽も駆使し、さらには音量豊かな声楽も加味されたストーン・ミュージックと呼ばれるパフォーマンスをともなう音楽表現には、ミティラー美術館のコレクションと同じく「過去と現代」、そして「美術と音楽の出会い」が実現されている。1973年6月の『美術手帖』では、「小杉武久と『タージ・マハル旅行団』」の特集も組まれていた。
本展でも、会期中に「タージ・マハル旅行団からミティラー美術館へ」と題して、「長谷川時夫トーク&ライブ」が、電子音楽研究家で『ストーン・ミュージック 長谷川時夫の音楽』(engine books、2021年)の著者でもある川崎弘二氏のイントロダクションからはじめられた(2022年11月5日に開催した)。
そして私は、ここでもこのインドの展覧会を介して、先の大阪市立工芸学校にもかかわるバウハウスをキーワードに「展覧会の連なり」を感じるのである。先にも掲げた同校創立60周年記念誌『芸草』の1958年の記録には、新たな写真工芸科の校舎が紹介されているが、驚いたのは、その威容が、よく知られたバウハウス・デッサウのバルコニー部を模したのではないかとも思われるほど新鮮に感じられることである。早川良雄の回想もあるように、創立当初から同校では、東京高等工芸学校を卒業して赴任した山口正城が、まさに本邦初ともいうべきバウハウス流の指導による授業を行なっていたという。
そのバウハウスの教育実践は、日本とともにインドでも試みられた。そのことは、2018年に、京都国立近代美術館で開催された「バウハウスへの応答」展でも明らかにされていた。このことを、私は「ミティラー美術館展」で思い出し、それが「とびたつとき」展や「稗田一穗展」でも、意外な「展覧会の連なり」として実感した次第である。
いつの時代も、新たな芸術表現は「過去」との対峙の上に成り立つ。いわば「過去と現代が遭遇」し、それを乗り超えようとする意志が、新しい表現を生みだす。特に「近代」以降、その傾向は顕著であり、いわゆる「前衛」という果敢な行為がそれをもっとも顕著に特徴づける。
長谷川時夫館長が、音楽そして美術の領域で行われてきた活動も、「前衛」そのものにほかならない。今回のトーク&ライブ・ショーも、それを実現したものであり、「近代美術館」こそが、そうした活動をもっとも鮮明に打ち出せる場であるだろう。
(山野英嗣)
タグ:和歌山県立近代美術館, momaw, 稗田一穗, ミティラー美術館コレクション展, デモクラート